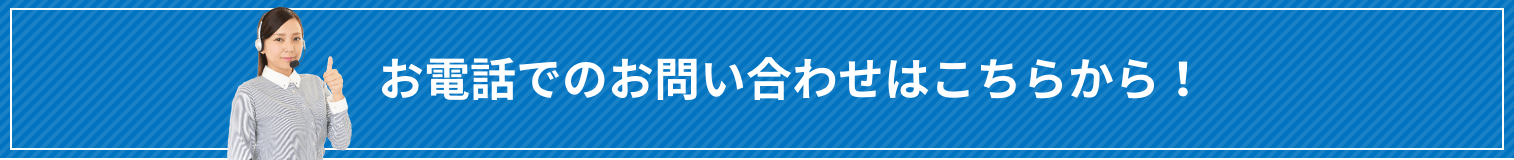屋上防水の種類別メリット・デメリットから適切な工事を解説!
屋上は、建物の最上階に位置し、雨風や紫外線に直接さらされる過酷な環境下にあります。
そのため、適切な防水対策が施されていないと、雨漏りや建物の劣化につながりかねません。
屋上防水工事は、建物の寿命を左右する重要な要素であり、適切な工事を行うことで、建物の資産価値を維持し、快適な生活空間を確保できます。
この記事では、屋上防水の種類、劣化症状、工事のポイント、メンテナンス方法などについて詳しく解説していきます。
管理会社や賃貸物件のオーナーなど、屋上の防水工事について詳しく知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
屋上防水の種類と特徴
屋上防水の工事には、主に4つの種類があります。
それぞれの工事の特徴、メリット、デメリットを解説します。
1: FRP防水
FRP防水とは、ガラス繊維で強化したプラスチックを屋上一面に塗りつける施工方法です。
耐用年数は10年~15年程度とされています。
・メリット
FRP防水は、耐久性と防水性に優れており、軽量素材のため建物への負担が少ない点がメリットです。
また、硬化するまでの時間が短いため、施工日数が1日程度と短く、比較的安価に施工できる点も魅力です。
・デメリット
一方で、FRP防水は伸縮性に乏しいため、建物の揺れによってひび割れが発生する可能性があります。
また、施工不良や経年劣化によって、防水層が剥がれてしまう可能性もあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
2: ウレタン防水
ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り広げ、防水層を形成する施工方法です。
耐用年数は5年~15年程度とされています。
・メリット
ウレタン防水は、屋上の形状を問わず施工できる柔軟性があり、複雑な形状の屋上でも継ぎ目のない仕上がりが期待できます。
また、硬化スピードが速く、施工日数が短縮できる点もメリットです。
・デメリット
ウレタン防水は、施工不良によって膨れやひび割れが発生する可能性があります。
また、職人の技術力によって防水層の厚さにばらつきが生じる可能性もあるため、信頼できる施工業者を選ぶことが重要です。
3:シート防水
シート防水は、塩化ビニールシートやゴム製シートなどを貼り付け、防水層を形成する施工方法です。
耐用年数は10年~15年程度とされています。
・メリット
シート防水は、職人によって仕上がりに差が出にくいという特徴があります。
また、耐熱性や耐紫外線性に優れており、耐久性が高い点も魅力です。
さらに、古い防水層の上から施工できるため、下地処理が不要で施工期間が短縮できます。
・デメリット
シート防水は、複雑な形状の屋上への施工が難しい場合があります。
また、施工不良や経年劣化によって、シートが剥がれてしまう可能性もあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
4: 塗膜防水
塗膜防水とは、液体状の塗料を屋上に複数回塗り重ね、防水層を形成する施工方法です。
耐用年数は5年~10年程度とされています。
・メリット
塗膜防水は、比較的安価に施工できる点と、既存の防水層の上から施工できる点がメリットです。
また、カラーバリエーションが豊富で、建物の外観に合わせて選べます。
・デメリット
塗膜防水は、耐久性が他の防水方法に比べて低いという点がデメリットです。
また、施工不良によって剥がれやひび割れが発生する可能性もあるため、信頼できる施工業者を選ぶことが重要です。

屋上防水工事が必要な劣化症状
屋上防水工事が必要となる劣化症状には、次のようなものがあります。
1: 色あせ
屋上防水の塗装は、紫外線や雨風によって経年劣化し、色あせてきます。
色あせは、防水層の劣化を示すサインであり、放置すると雨漏りや建物の劣化につながる可能性があります。
2: ひび割れ
ひび割れは、建物の揺れ、温度変化、施工不良などによって発生します。
ひび割れから水が浸入すると、雨漏りや建物の腐食につながるため、早期の修理が必要です。
3: 剥がれ
剥がれは、防水層の劣化や施工不良によって発生します。
剥がれた部分から水が浸入すると、雨漏りや建物の劣化につながるため、早急な修理が必要です。
4: 膨れ
膨れは、ウレタン防水やシート防水などで発生する症状です。
防水層の中に空気が溜まって膨らむことで、ひび割れや剥がれが発生しやすくなります。
5: 水溜まり
水溜まりは、排水口の詰まりや勾配不良などによって発生します。
水溜まりは、防水層に負担をかけ、雨漏りや建物の劣化の原因となります。
6: ドレン周りや笠木の劣化
ドレン周りや笠木は、雨水の排水や建物の保護に重要な役割を果たしています。
これらの部分が劣化すると、雨漏りや建物の劣化につながるため、定期的な点検が必要です。
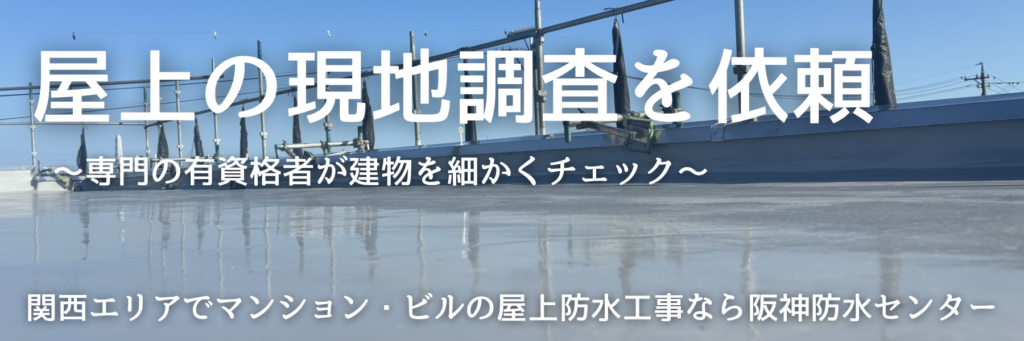
大規模修繕での屋上防水のポイント
大規模修繕で屋上防水工事を行う際には、以下のポイントを押さえることが重要です。
1: 完璧な防水層の形成
大規模修繕では、屋上防水層を完全に新しく作り直すため、使用する材料や施工方法を慎重に検討する必要があります。
2:適切な材料の選択
防水層の材料には、FRP防水、ウレタン防水、シート防水、塗膜防水など、さまざまな種類があります。
建物の構造や用途、予算などを考慮して、最適な材料を選択することが重要です。
3:丁寧な施工
施工の際には、丁寧な作業を行うことが重要です。
施工不良は、雨漏りや防水層の早期劣化につながるため、信頼できる施工業者に依頼することが重要です。
4:丁寧な検査
施工完了後は、必ず検査を行い、防水層に問題がないことを確認する必要があります。
検査では、目視検査に加えて、水密検査などを行うのが一般的です。
・目視での検査
目視検査では、防水層の表面にひび割れや剥がれがないか、排水口に詰まりがないかなどを確認します。
・水密検査
水密検査では、防水層に水を溜めて、水漏れがないかを確認します。
5:アフターフォロー
工事完了後も、定期的な点検やメンテナンスを行うことが重要です。
アフターフォローが充実している業者を選ぶことで、安心して屋上防水の施工を任せられます。
6:定期点検
定期点検では、防水層の劣化状況や排水口の詰まりなどを確認します。
7: メンテナンス
メンテナンスでは、ひび割れや剥がれの補修、排水口の清掃などを行います。

屋上防水を長持ちさせるコツ|メンテナンス方法
屋上防水を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
1: 定期的な点検
定期的に屋上を点検し、劣化や異常がないか確認することが重要です。
・点検の頻度
点検の頻度は、建物の構造や用途、防水層の種類などによって異なりますが、少なくとも年に1回は点検を行うようにしましょう。
・点検項目
点検項目は、防水層の表面、排水口、ドレン周り、笠木など、屋上のあらゆる箇所をチェックする必要があります。
2: 排水溝周りの清掃
排水溝は、雨水を集めて排水する重要な役割を果たしています。
排水溝が詰まると、水溜まりが発生し、防水層に負担がかかり、雨漏りの原因となるため、定期的に清掃することが重要です。
3: トップコートの塗り替え
塗膜防水の場合、定期的にトップコートを塗り替えることで、防水層の耐久性を維持することができます。
・塗り替えのタイミング
塗り替えのタイミングは、防水層の状態や使用されている塗料の種類によって異なりますが、目安として5年~10年程度です。
・塗り替えの費用
塗り替え費用は、防水層の面積や使用される塗料の種類によって異なります。
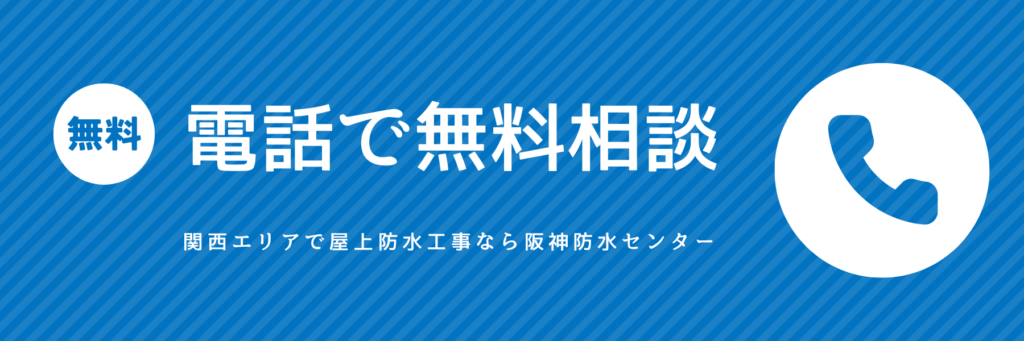
まとめ
この記事では、屋上防水の種類、劣化症状、工事のポイント、メンテナンス方法について解説しました。
屋上防水は、建物の寿命を左右する重要な要素であり、適切な工事を行うことで、建物の資産価値を維持し、快適な生活空間を確保できます。
屋上防水工事の依頼を検討する際は、信頼できる施工業者を選び、丁寧な施工、検査、アフターフォローを行うようにしましょう。
また、定期的なメンテナンスを行うことで、屋上防水の寿命を延ばすことができます。
屋上防水について詳しく知りたい方は、専門業者に相談することをおすすめします。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
マンション、ビルの屋上防水なら阪神防水センターにお任せ下さい!
阪神防水センターはビルやマンションの防水工事に特化した専門企業です。
お客様の大切な建物をしっかりと守るために、最適な防水工法をご提案いたします。
大阪・神戸を中心に関西エリアでの防水工事をお考えでしたらまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料・診断無料・見積もり無料
お電話の場合はこちら:0120-69-1670
メールの場合はこちら:お問合せ専用フォーム
屋上の無料診断はこちら:無料診断依頼用フォーム
料金表についてはこちら:工事メニュー別の料金ページ
施工事例も定期的に更新しておりますのでぜひご覧ください!
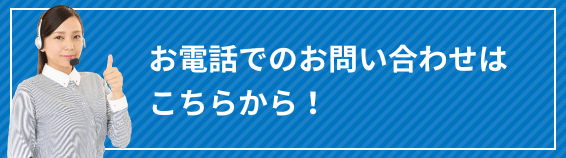
お気軽にお電話ください

 一覧へ戻る
一覧へ戻る